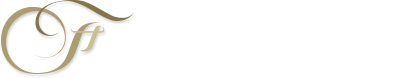レーザーの歴史
① レーザー発想の誕生と黎明期
② レーザー脱毛器の誕生
③ あざやほくろに効くレーザーの登場
④ 画期的な色彩的老化の治療法 IPL の登場
⑤ 形態的老化へのアプローチ RF の登場の歴史
⑥ 肌を入れ替える スキンリサーフェシングレーザーの登場
⑦ レーザーによる肝斑治療
⑧ アブレイティブ・フラクショナルレーザー機器の登場
⑨ アンチエイジング市場におけるレーザーの躍進
⑩ 「レーザーアンチエイジング」というジャンルの確立~フラクショナルレーザー登場による市場の変化・拡大
⑪ HIFUによるリフトアップ効果がFDAで承認
⑫ ピコ秒レーザーの誕生
⑬ 伊DEKA社の躍進とhaloの登場
⑭ フラクショナルレーザーによる新たな道筋「ドラッグデリバリー」
⑮ レーザー治療は遺伝子に影響を与えるのか
⑯ レーザーによる痩身市場の開拓
⑰ 粘膜に照射する美容レーザーの誕生
⑱ HIFEMの登場
ピコ秒レーザーの誕生
僕の記憶にある限り、美容系の学会でピコ秒レーザーが登場したのは2013年、マイアミで開催されたAAD米国皮膚科学会が最初です。

レーザー医工学の面白い点は、レーザーの波長、パルス幅(照射時間)、フルレンス(照射エネルギー密度)によって生体の物質に対して選択性を持たせられることにつきます。
●皮下のどの深さの、どの直径のメラニンに対して効果を出すのか?
●表皮のニキビ跡を、どの波長を利用して削るのか?
●下肢静脈瘤をどのように破壊するか?
・・・などなど。
レーザー工学を語る上でもう一つ大切なものがあります。
それは発振モードです。
レーザー発振モードは大きく二つに分けられます。
① 連続波レーザー(CW)
② パルス波レーザー(PW)
というものです。
CWレーザーは一定の出力が連続的に照射される発振方法で、レーザーの光熱的作用を利用する際に使われます。
レーザー光の強さである「照射出力」は1秒間のレーザー出力であるWで表現される「放射出力」と同義になります。
一方で、エネルギー照射量を制御したい場合はパルス波(PW)レーザーを使用することが多くなります。
こちらのパルス波レーザーは、一秒間に一定幅のパルス幅を持った単パルスが一定間隔で繰り返し発射される発振法です。
1秒からスタートして、照射時間を1000分の1に短くしてゆくと
秒→ミリ秒→マイクロ秒→ナノ秒→ピコ秒→フェムト秒→アト秒
・・・と、呼び名が変わるのです。
ちなみに工学系ではピコ秒の百万分の一の単位であるアト秒レーザー機器まで開発されています。
アト秒レーザー機器を使用すると、分子ばかりか原子の動きまでを測定できるのです。パルス幅に関しては、医療レーザーとは隔世の感がありますね。
今まで医療の分野ではナノ秒発振機器が最短でした。
工学的には、こちらはパルスの幅によって大きく3種類に分けられています。
パルス幅が
◆10ミリ秒以上のものを ロングパルス
◆マイクロ秒レベルを ノーマルパルス
◆ナノ秒~フェムト秒レベルを ショートパルス
と言います。
同じように、パルス幅が
◇10ミリ秒以上のものを チョップドパルス
◇マイクロ秒レベルを スーパーパルス
◇ナノ秒~フェムト秒レベルを Qスイッチパルス
と呼ぶこともあります。
こうして定義から考えますと、ピコ秒レーザーは「Qスイッチレーザーの一種である」と言えるのですよね。
2015年の米国レーザー医学会では、臨床で使用されているピコレーザー機器の演題が多く、興味深い学会となりました。

米国レーザー医学会では数多くのレーザーが発表されますが、2015年も引き続きトピックの一つはピコ秒レーザーと言えるでしょう。

レーザーを選択するにあたり、波長とともに大切なファクターにパルス幅があります。
機器の開発とともに
〇ミリ秒(1/1000秒) 〇マイクロ秒(1/1000000秒) 〇ナノ秒(1/1000000000秒) 単位でレーザーの照射検証が行われてきました。
特に、ナノ秒発振が可能で数kHzの繰り返し周波数で動作するものを「ナノ秒Qスイッチレーザー」と言います。 ナノ秒レーザーの利点として挙げられるのは、従来技術が確立されており、ツールとしての信頼性が高いという点、かつランニングコストが抑えられる点です。
一方、昨年よりナノ秒からさらに3桁下の秒数で発振することの可能なレーザーが皮膚科形成外科領域にも登場しました。 それが、ピコ秒(1/1000000000000)発振の可能なレーザーです。
このピコ秒の話をするために、米国レーザー医学会の重鎮の一人、ロバート・ワイス医師が話した内容とそれに使用していたスライドが興味深かったです。

もしもロングパルスアレキサンドライトレーザーのパルス幅をニューヨークからロサンジェルス間の距離と想定すると、
■Qスイッチアレキサンドライトレーザーは大型トラックの荷台の大きさ
それに対し
■750ピコ秒レーザーはコーラのボトルの大きさに相当する
と言ったのです。
これを聞いて僕はうーんと唸ってしまいました。
自分が関わっているレーザー/光治療という学問が、近未来的なものであるという認識はこれまでもありましたが、こうして土地とトラック、コーラという全然違うもの、完全に異なるものを出さざるを得ないほど、比較することができない、単位も桁も全く違う、これまでの想像や常識を超えた物差しでもって次々に進化を遂げていく、それこそが僕の選んだ研究対象であり、学問だということなのです。
未来へ未来へとレーザー医療が先に進んでいく姿を、今回も目の当たりにしました。こうして話題と注目を集めるピコ秒レーザーですが、具体的な機器を挙げると
昨年CYNOSURE社で販売が始まったPICOSURE(ピコシュア)755nm
本年より追従した
CUTERA社のENLIGHTEN(エンライトン) 1064/532nm
SYNERON/CANDELA社のPICOWAY(ピコウェイ) 1064/532nm
といったものが現在市場に出ていてある程度定評を確立しつつあるものと言えます。
エンライトンの最大出力は 600mJ (1064nm) 300mJ (532nm)
パルス幅 750ps
ピコウェイの最大出力は 400mJ (1064nm) 200mJ (532nm)
パルス幅 450ps (1064nm) 375ps (532nm)
ですので、ピコウェイのパルス幅は他社に比較して短く、魅力がありますね。
以前医療レーザー開発者と、理論上最適なピコ秒の幅を想定した際には、 380-420ps のレンジで 1000mJの出力が確保できれば理想だと聞いたことがありますので、工学的にはもう少し発展を待ちたいところではあります。
ピコ秒などの短パルスレーザーであれば、瞬間的にとても高いピークパワーを持つため、多光子吸収が発生し、材料の電子を励起させ直接原子結合を分解します。
さらに、熱が拡散する時間よりパルス幅が短いため、熱影響が広がりにくい。 工学的にも、ピコ秒レーザーによる加工は、長いパルス幅を持つレーザーに比べ、材料を瞬時に蒸発させることにより溶融物の発生を低減させます。
そこで材料に対して熱影響の少ない、精密な加工ができるのです。
医学的にピコ秒があると唯一メリットがあると発表されているのは、刺青の治療のみ。 期待していた肝斑の治療については、もう少し議論が必要なようです。

こちらシネロンキャンデラ社のピコウェイ

長年キャンデラの機器開発に携わっている工学博士のDr.Bhowalkorと写真を撮りましたよ。 ピコウェイの開発秘話なども聞くことができました。
2016年のボストンでの米国レーザー医学会では、トランプ旋風の元、
ピコレーザーのセッションだけでじっくり3時間。
色素粒子の小さい刺青についてはかなり良い結果が出ているようです。
波長の使い分けとしては532nmピコが赤、オレンジ、黄の刺青。
755nmピコが青とグリーンの刺青。
1064nmは黒の刺青により効果があるということでした。
光の波長はnm単位ものもが多いのですが、粒子が光の波長よりも短くなると、理論上はカラーブラインドと言って、色素の色に関係なく破壊が行われるだろうと予測されていたのですが、残念ながら当初のメーカー発表のような完全なカラーブラインドというわけではなさそうですので、ピコ秒を選択してもやはり数波長が必要という発表でしたね。
一方色素斑に関しては、機器の値段ほどの差は無いのではという意見が大半でした。
ナノ秒は熱効果が高いためにリジュビネーション(肌の若返り)効果が期待できる一方、ピコ秒は周辺組織に対して熱ダメージが無いが副作用が少ないという特徴があり、両者はtrade-offの関係にあると言うのが結論ですね。
この原稿を書いている2018年に現状発売されている機種は、ピコ秒とは言っても3桁代のピコ秒。つまり0.3ナノ秒ぐらいの機種が多いのですが、工学的には2桁のピコ秒が実現するとプラズマ化して反応しますので、今までの選択的光融解理論とは違った反応がみられるはずです。
今後、色素斑に対してピコ秒がどのように使われてゆくのか興味深いところですね。
※当サイトのテキスト&画像の無断転載はお断りいたします。引用される場合はクリニックFのクレジット記載をお願いいたします。